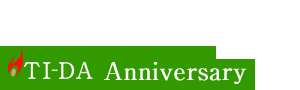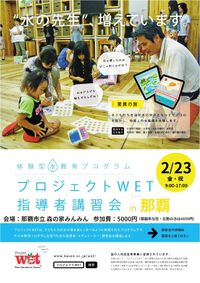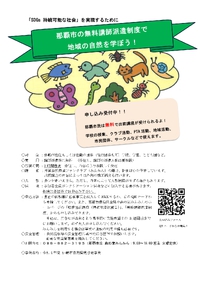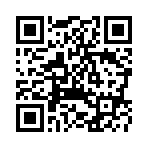2023年02月03日
2/3 「シカと技術者倫理」のコラムのご紹介
おはようございます。
昨日、興味深い記事(コラム)を見つけました。
日本機械学会さんのHPに掲載されている『シカと技術者倫理』というコラムです。
色々と考えさせられ、面白かったのでご紹介します。
『シカと技術者倫理』
https://www.jsme.or.jp/eec/uploads/sites/5/2021/03/20201221.pdf
(上記資料からの引用)「シカと列車の衝突防ぎます!日鉄住金建材が生態を研究し尽くした防護柵とは」
(https://newswitch.jp/p/2317)
簡単にコラムの内容を説明しますと、県外では電車の線路にシカが入ってしまい、残念ながら交通事故に遭ってしまうケースが少なくないようです。
その事故を減らそうと、「なぜシカは餌が無いのに電車の線路に入ってくるのか?」「防ぐことはできないか?」と技術者(日鉄建材の技術者・研究者の皆さん)が原因を突き止め、シカの防護柵を作ったというエピソードでした。
(興味深いのでぜひコラムや新聞ニュースをご一読ください)
前述のコラムやニュースをざっくり説明すると、シカが線路に含まれる鉄分を舐めにくることを突き止め、その行動パターンを踏まえてシカが鉄分を補給する場所を作ったり、シカが飛び込えやすい低い高さの防護柵を作ったというものでした。
この話でふと思ったのが、末吉公園にもたくさんあるグリーンアノールトラップについてでした。
グリーンアノールのトラップは、粘着剤を塗布したシートが用いられており、グリーンアノールが付着するようになっています。
他の生き物、アオカナヘビやオキナワキノボリトカゲ、ヤモリや昆虫類、そして小鳥やヘビもかかってしまうことがあります。
(間違って対象以外の他の生き物がかかってしまうことを混獲(錯誤捕獲)といいます。)
シカのコラムを読んで、生きものの生態や行動特性を利用して混獲を減らせないかなと思いました。
ちなみに、土木や機械関係の技術者というと、モノを作ったり技術を開発したりというイメージや、人の安全や健康を重視するという印象が強かったのですが、生物を守るという視点から開発を続けていたこともちょっと感慨深かったです。
この「シカの衝突防ぎます」のニュース記事によると、この研究チームは北は北海道から京都まで大学や研究機関を渡りヒアリングなどをして、シカについて調べたり、実証実験も行ったそうです。
成果として新聞記事には、「2013年から14年にかけ、岐阜県内で実証実験を行ったところ、侵入件数はその前の同じ月の半年間で171件が4件に激減」とありました。(素晴らしいですね!! )
)
みんみんでも、小鳥が間違ってトラップにかかってしまうのを防ぐために、藤井さんが提案して防鳥テープ(農業用)や目玉模様のシールをつけてみたことがあります。
結局、2つの罠だけだったので効果のほどは不明ですが、コレ!という方法があればいいなと思います。

▲ トラップにかかってしまった小鳥 (助けられました。)
みんみんはにほんブログ村に参加中。ポチっと押して頂けるとスタッフの励みになります&見る人が少し増えます。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村
昨日、興味深い記事(コラム)を見つけました。
日本機械学会さんのHPに掲載されている『シカと技術者倫理』というコラムです。
色々と考えさせられ、面白かったのでご紹介します。
『シカと技術者倫理』
https://www.jsme.or.jp/eec/uploads/sites/5/2021/03/20201221.pdf
(上記資料からの引用)「シカと列車の衝突防ぎます!日鉄住金建材が生態を研究し尽くした防護柵とは」
(https://newswitch.jp/p/2317)
簡単にコラムの内容を説明しますと、県外では電車の線路にシカが入ってしまい、残念ながら交通事故に遭ってしまうケースが少なくないようです。
その事故を減らそうと、「なぜシカは餌が無いのに電車の線路に入ってくるのか?」「防ぐことはできないか?」と技術者(日鉄建材の技術者・研究者の皆さん)が原因を突き止め、シカの防護柵を作ったというエピソードでした。
(興味深いのでぜひコラムや新聞ニュースをご一読ください)
前述のコラムやニュースをざっくり説明すると、シカが線路に含まれる鉄分を舐めにくることを突き止め、その行動パターンを踏まえてシカが鉄分を補給する場所を作ったり、シカが飛び込えやすい低い高さの防護柵を作ったというものでした。
この話でふと思ったのが、末吉公園にもたくさんあるグリーンアノールトラップについてでした。
グリーンアノールのトラップは、粘着剤を塗布したシートが用いられており、グリーンアノールが付着するようになっています。
他の生き物、アオカナヘビやオキナワキノボリトカゲ、ヤモリや昆虫類、そして小鳥やヘビもかかってしまうことがあります。
(間違って対象以外の他の生き物がかかってしまうことを混獲(錯誤捕獲)といいます。)
シカのコラムを読んで、生きものの生態や行動特性を利用して混獲を減らせないかなと思いました。
ちなみに、土木や機械関係の技術者というと、モノを作ったり技術を開発したりというイメージや、人の安全や健康を重視するという印象が強かったのですが、生物を守るという視点から開発を続けていたこともちょっと感慨深かったです。
この「シカの衝突防ぎます」のニュース記事によると、この研究チームは北は北海道から京都まで大学や研究機関を渡りヒアリングなどをして、シカについて調べたり、実証実験も行ったそうです。
成果として新聞記事には、「2013年から14年にかけ、岐阜県内で実証実験を行ったところ、侵入件数はその前の同じ月の半年間で171件が4件に激減」とありました。(素晴らしいですね!!
 )
)みんみんでも、小鳥が間違ってトラップにかかってしまうのを防ぐために、藤井さんが提案して防鳥テープ(農業用)や目玉模様のシールをつけてみたことがあります。
結局、2つの罠だけだったので効果のほどは不明ですが、コレ!という方法があればいいなと思います。

▲ トラップにかかってしまった小鳥 (助けられました。)
みんみんはにほんブログ村に参加中。ポチっと押して頂けるとスタッフの励みになります&見る人が少し増えます。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
Posted by 森の家みんみん at 12:09│Comments(0)
│スタッフのつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。