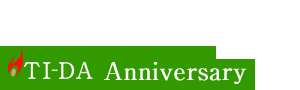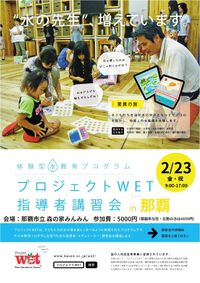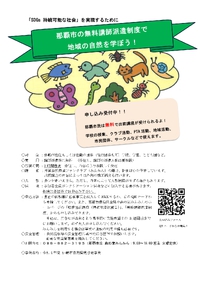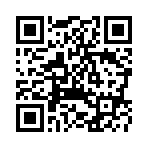2022年09月17日
8/22イベント「小動物をとおして観た末吉の森~キノボリトカゲを中心として~」
こんにちは
遅くなりましたが8/22に行われたイベント「小動物をとおして観た末吉の森~キノボリトカゲを中心として~」の様子をレポートします
当日は夏休みということもあり、小学生から大学院生、末吉公園の近所にお住まいの方、那覇市の方など色々な方がご参加下さいました。

講師は田中聡先生(元沖縄県立博物館・美術館 主任学芸員)です。

▲説明する田中先生
田中さんは大学・大学院での研究で、また勤務される傍ら、長年キノボリトカゲやクロイワトカゲモドキなどを調査されてきました。
昨年からキノボリトカゲの勉強会をして頂けませんかとお伺いしていたこともあり、今回のイベントではコロナ禍にもかかわらず快くお引き受け下さいました
田中先生、ありがとうございます

当日のイベントは、①室内での講話(末吉の森にすんでいるキノボリトカゲやクロイワトカゲモドキについて詳しくお話を聞く)
→②野外でキノボリトカゲを実際に探して観察しよう!という流れです。
--------------------------
田中先生のお話紹介
--------------------------
当日、お仕事のために参加出来なかった方もいらっしゃったので田中さんのお話を少しだけご紹介します。
田中先生は、今から約40年前、1977年~1979年に「クロイワトカゲモドキの生活史・生態について」、1980年~1981年と1982~1984年に「キノボリトカゲの社会構造」をテーマとして末吉公園で研究を行いました。

▲田中先生の40年前の研究(末吉の森)
【キノボリトカゲのお話】
研究では、キノボリトカゲの生息個体数やオスの行動、なわばりを形成したオスとなわばりを形成していなオスがいることや、なわばりオスができるだけ多くのメスを確保するようなわばりを形成することによる一夫多妻制という配偶システムをもつことなどを詳しく調べたそうです。
キノボリトカゲは、見つけた個体を1個体ずつマーキングして個体識別した結果、末吉の森の林内の一区画(2,200㎡)におよそ100個体の成体を確認したそうですよ。
その後、田中先生は2002年や2022年にも末吉の森で調査をしています。
キノボリトカゲの同エリアでの生息個体数は、約40年後の調査では1980年代と比べて半数程度に減少していたと仰っていました。
1980年頃の調査で「分かったこと」として次のようなことを教えて下さいました。
 調査区域内(面積2,200㎡)の中にオス42個体、メス58+αが確認された。
調査区域内(面積2,200㎡)の中にオス42個体、メス58+αが確認された。
 オスのなわばりは他のオスのなわばりとほとんど重複していない。
オスのなわばりは他のオスのなわばりとほとんど重複していない。
 なわばりに別のオスが侵入してくると、威嚇したり噛んで追い払う行動をとる。
なわばりに別のオスが侵入してくると、威嚇したり噛んで追い払う行動をとる。
 オスがなわばりを形成しているところと、なわばりを形成していないところを比べると、なわばりを形成している場所の方がメスの数が多い。
オスがなわばりを形成しているところと、なわばりを形成していないところを比べると、なわばりを形成している場所の方がメスの数が多い。
(オスがなわばりを形成しているところのメス 48個体) > (なわばりを形成していないところのメス 10個体)
ちなみに田中先生は2022年に外来植物のポトスが昔と比べて幹や林床を覆っているのに気づき、調査をされていました。
ポトスは2002年の調査時には末吉の森のごく一部にひっそりとしか生えてなかったそうです。
それが今では広範囲に広がっていて、林床を覆い、幹にもつるや葉を茂らせています。
体高が高く、腹面を底質から離して歩行・疾走するクロイワトカゲモドキやキノボリトカゲにとって、ポトスの繁茂はかれらの行動を強く阻害する可能性がとても高いと仰っていました。
キノボリトカゲが昔と比べて減少した原因として、
①人による捕獲 ②野良ネコによる捕食 ③外来植物ポトスの繁茂による生息場所の劣化 などを挙げていました。
---------------------
お話のまとめ
----------------------
最後に、「末吉の森をより良い姿で残すために」として、
私たちができることや行政に期待することをいくつかお話されていました。
(行政の方への期待)
〇ポトスについては、早急に予算措置を行い駆除作業を実施するとともに、こういう植物が野外に放置されるとどういうことになってしまうかを県民に広く周知してほしい
〇ノラネコ対策
〇違法採集に対する対策
(やってはいけないこと)
〇林内の落葉落枝の除去
〇外来植物の植栽と在来植物のむやみな刈り取り
(一般の皆さんへのおすすめ)
自分のお気に入りの生き物についてモニタリングしてみては?
そういうことを通して、誰かが異変に気付き、情報を共有し、課題解決を目指せるように。

▲まとめのスライド
お話の後は、いよいよ野外で観察です

中学生も含めて大人20名ほど、警戒心が強いキノボリトカゲは出てきてくれるのか

心配するスタッフ&藤井さんをよそに、目の良い田中先生と参加者は次々とキノボリトカゲを発見していました。良かった )
)


▲キノボリトカゲ
田中先生が1980年代に調査された区域をゆっくり歩いてみて回り、急激に増えている外来植物「ポトス」も実際に見てみました。

▲ポトスで覆われたヤバい林内
このポトス、20年前にはごく狭い範囲だけにみられたそう。
先に述べたように、急激に増えている、ポトスは幹にツルを巻き付けて大きな葉を広げるのでキノボリトカゲの繁殖行動や採餌(さいじ)に影響があると思う、これ以上広がる前にすみやかに除去した方が良いそうです。
観察が終わった後は、皆さんからの感想や質問コーナー、みんみん藤井さんからのまとめもあって終了しました。

▲ふりかえりをする藤井さん (末吉公園で一緒に活動しましょう、ご協力お願いしますというようなお話をされていました)
追記
ご参加者からの感想もご紹介します。
「今回の講座で、自分の身の周りの自然環境にも着目して、その問題点や解決点についてもっと深く考えてみようと思いました」
「トカゲに対する興味が湧きました」
「外来生物というとグリーンアノールなど動物をイメージしますが、植物ポトスがうっそうと茂る場所、末吉公園を見て沖縄の自然を今一度考えさせられました。」
「キノボリトカゲが見られて嬉しかったです。キノボリトカゲを守るためにもアノールを減らすことをがんばらないとなあと改めて思いました。」
このイベントは、一昨年から末吉公園で駆除対策がとられている特定外来生物「グリーンアノール」のトラップに、
キノボリトカゲが誤ってかかってしまう問題(混獲)をきっかけに企画したものです。
そのこともあり、ご参加者から頂いた感想の中にはグリーンアノールについてのものもありました。
「生きものが好きなので自宅にいるグリーンアノールを駆除するのは可哀想と思ってしまう。」
「必要と分かっていても殺してしまうのに抵抗がある」
ちょうど沖縄自然環境ファンクラブでもグリーンアノールの駆除に取り組んでいるところなので、
ご参加者の気持ちが良く分かりました。
特定外来生物のグリーンアノールを駆除しなければならない理由は、
①沖縄の昆虫を捕食するため
②沖縄のトカゲと餌やすみかを奪って競合するため
③やんばるや離島へのグリーンアノールの分布拡大を防ぐため などとされています。
(沖縄県の防除目標は「拡散リスク低減」)
そうは言っても、普通の市民にとっては外来生物とはいえ、動物を駆除することに抵抗があると思います。
スタッフの個人的な意見ですが、上記の3つに加えて、
グリーンアノールは繫殖力が強く、短期間で数倍に増える(飼育下で1年で20回産卵したデータがあるそうです)、
だから今、グリーンアノールを駆除しなければどんどん数が増えて駆除しなければならないグリーンアノールの数がもっと増える、
そのため、かわいそうと思っても今、駆除した方が良いと思ってやっています、というような話をお伝えしました。
また、1人で外来生物対策(動物の駆除)をするのは気が重いので、みんなで、チームでやった方が良いと思いますという話や
実際の捕獲が苦手であれば、得意な普及啓発の方で協力をしてはどうですかという話をしました。
分かったような気がすると仰って下さった参加者さんもいて、少し安心しました。
最後になりましたが、
このイベントの目的は
「中南部の自然は、やんばるの自然とはまた違う特徴があって貴重だということを理解する」
「身近な自然に異変が起きた時に気づく目を養い、モニタリングすることの重要さを知る」というものでした。
ご参加された皆さんが身近な中南部の自然について考えたり、活動するきっかけになってくれれば良いなあと思います。
みんみんでも一緒に活動してくれる仲間を募集中です
【 ご紹介 田中聡先生が著者・共著の報文 】
「なわばりを守る雄 キノボリトカゲ」朝日百科 動物たちの地球102 両生類・爬虫類6 pp.178-180 朝日新聞社(1993)
「湿潤な亜熱帯の森でひっそりと生きる クロイワトカゲモドキ」 森林技術 No.766 2006.1
「レッドデータおきなわ 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第3版(動物編) 」
p193-194 キノボリトカゲ、p191-193クロイワトカゲモドキ
(URL : https://www.okinawa-ikimono.com/reddata/pdf/doubutsu2017.pdf)
遅くなりましたが8/22に行われたイベント「小動物をとおして観た末吉の森~キノボリトカゲを中心として~」の様子をレポートします

当日は夏休みということもあり、小学生から大学院生、末吉公園の近所にお住まいの方、那覇市の方など色々な方がご参加下さいました。
講師は田中聡先生(元沖縄県立博物館・美術館 主任学芸員)です。
▲説明する田中先生
田中さんは大学・大学院での研究で、また勤務される傍ら、長年キノボリトカゲやクロイワトカゲモドキなどを調査されてきました。
昨年からキノボリトカゲの勉強会をして頂けませんかとお伺いしていたこともあり、今回のイベントではコロナ禍にもかかわらず快くお引き受け下さいました
田中先生、ありがとうございます


当日のイベントは、①室内での講話(末吉の森にすんでいるキノボリトカゲやクロイワトカゲモドキについて詳しくお話を聞く)
→②野外でキノボリトカゲを実際に探して観察しよう!という流れです。
--------------------------
田中先生のお話紹介
--------------------------
当日、お仕事のために参加出来なかった方もいらっしゃったので田中さんのお話を少しだけご紹介します。
田中先生は、今から約40年前、1977年~1979年に「クロイワトカゲモドキの生活史・生態について」、1980年~1981年と1982~1984年に「キノボリトカゲの社会構造」をテーマとして末吉公園で研究を行いました。
▲田中先生の40年前の研究(末吉の森)
【キノボリトカゲのお話】
研究では、キノボリトカゲの生息個体数やオスの行動、なわばりを形成したオスとなわばりを形成していなオスがいることや、なわばりオスができるだけ多くのメスを確保するようなわばりを形成することによる一夫多妻制という配偶システムをもつことなどを詳しく調べたそうです。
キノボリトカゲは、見つけた個体を1個体ずつマーキングして個体識別した結果、末吉の森の林内の一区画(2,200㎡)におよそ100個体の成体を確認したそうですよ。
その後、田中先生は2002年や2022年にも末吉の森で調査をしています。
キノボリトカゲの同エリアでの生息個体数は、約40年後の調査では1980年代と比べて半数程度に減少していたと仰っていました。
1980年頃の調査で「分かったこと」として次のようなことを教えて下さいました。
 調査区域内(面積2,200㎡)の中にオス42個体、メス58+αが確認された。
調査区域内(面積2,200㎡)の中にオス42個体、メス58+αが確認された。 オスのなわばりは他のオスのなわばりとほとんど重複していない。
オスのなわばりは他のオスのなわばりとほとんど重複していない。 なわばりに別のオスが侵入してくると、威嚇したり噛んで追い払う行動をとる。
なわばりに別のオスが侵入してくると、威嚇したり噛んで追い払う行動をとる。 オスがなわばりを形成しているところと、なわばりを形成していないところを比べると、なわばりを形成している場所の方がメスの数が多い。
オスがなわばりを形成しているところと、なわばりを形成していないところを比べると、なわばりを形成している場所の方がメスの数が多い。(オスがなわばりを形成しているところのメス 48個体) > (なわばりを形成していないところのメス 10個体)
ちなみに田中先生は2022年に外来植物のポトスが昔と比べて幹や林床を覆っているのに気づき、調査をされていました。
ポトスは2002年の調査時には末吉の森のごく一部にひっそりとしか生えてなかったそうです。
それが今では広範囲に広がっていて、林床を覆い、幹にもつるや葉を茂らせています。
体高が高く、腹面を底質から離して歩行・疾走するクロイワトカゲモドキやキノボリトカゲにとって、ポトスの繁茂はかれらの行動を強く阻害する可能性がとても高いと仰っていました。
キノボリトカゲが昔と比べて減少した原因として、
①人による捕獲 ②野良ネコによる捕食 ③外来植物ポトスの繁茂による生息場所の劣化 などを挙げていました。
---------------------
お話のまとめ
----------------------
最後に、「末吉の森をより良い姿で残すために」として、
私たちができることや行政に期待することをいくつかお話されていました。
(行政の方への期待)
〇ポトスについては、早急に予算措置を行い駆除作業を実施するとともに、こういう植物が野外に放置されるとどういうことになってしまうかを県民に広く周知してほしい
〇ノラネコ対策
〇違法採集に対する対策
(やってはいけないこと)
〇林内の落葉落枝の除去
〇外来植物の植栽と在来植物のむやみな刈り取り
(一般の皆さんへのおすすめ)
自分のお気に入りの生き物についてモニタリングしてみては?
そういうことを通して、誰かが異変に気付き、情報を共有し、課題解決を目指せるように。
▲まとめのスライド
お話の後は、いよいよ野外で観察です

中学生も含めて大人20名ほど、警戒心が強いキノボリトカゲは出てきてくれるのか


心配するスタッフ&藤井さんをよそに、目の良い田中先生と参加者は次々とキノボリトカゲを発見していました。良かった
▲キノボリトカゲ
田中先生が1980年代に調査された区域をゆっくり歩いてみて回り、急激に増えている外来植物「ポトス」も実際に見てみました。
▲ポトスで覆われたヤバい林内
このポトス、20年前にはごく狭い範囲だけにみられたそう。
先に述べたように、急激に増えている、ポトスは幹にツルを巻き付けて大きな葉を広げるのでキノボリトカゲの繁殖行動や採餌(さいじ)に影響があると思う、これ以上広がる前にすみやかに除去した方が良いそうです。
観察が終わった後は、皆さんからの感想や質問コーナー、みんみん藤井さんからのまとめもあって終了しました。
▲ふりかえりをする藤井さん (末吉公園で一緒に活動しましょう、ご協力お願いしますというようなお話をされていました)
追記

ご参加者からの感想もご紹介します。
「今回の講座で、自分の身の周りの自然環境にも着目して、その問題点や解決点についてもっと深く考えてみようと思いました」
「トカゲに対する興味が湧きました」
「外来生物というとグリーンアノールなど動物をイメージしますが、植物ポトスがうっそうと茂る場所、末吉公園を見て沖縄の自然を今一度考えさせられました。」
「キノボリトカゲが見られて嬉しかったです。キノボリトカゲを守るためにもアノールを減らすことをがんばらないとなあと改めて思いました。」
このイベントは、一昨年から末吉公園で駆除対策がとられている特定外来生物「グリーンアノール」のトラップに、
キノボリトカゲが誤ってかかってしまう問題(混獲)をきっかけに企画したものです。
そのこともあり、ご参加者から頂いた感想の中にはグリーンアノールについてのものもありました。
「生きものが好きなので自宅にいるグリーンアノールを駆除するのは可哀想と思ってしまう。」
「必要と分かっていても殺してしまうのに抵抗がある」
ちょうど沖縄自然環境ファンクラブでもグリーンアノールの駆除に取り組んでいるところなので、
ご参加者の気持ちが良く分かりました。
特定外来生物のグリーンアノールを駆除しなければならない理由は、
①沖縄の昆虫を捕食するため
②沖縄のトカゲと餌やすみかを奪って競合するため
③やんばるや離島へのグリーンアノールの分布拡大を防ぐため などとされています。
(沖縄県の防除目標は「拡散リスク低減」)
そうは言っても、普通の市民にとっては外来生物とはいえ、動物を駆除することに抵抗があると思います。
スタッフの個人的な意見ですが、上記の3つに加えて、
グリーンアノールは繫殖力が強く、短期間で数倍に増える(飼育下で1年で20回産卵したデータがあるそうです)、
だから今、グリーンアノールを駆除しなければどんどん数が増えて駆除しなければならないグリーンアノールの数がもっと増える、
そのため、かわいそうと思っても今、駆除した方が良いと思ってやっています、というような話をお伝えしました。
また、1人で外来生物対策(動物の駆除)をするのは気が重いので、みんなで、チームでやった方が良いと思いますという話や
実際の捕獲が苦手であれば、得意な普及啓発の方で協力をしてはどうですかという話をしました。
分かったような気がすると仰って下さった参加者さんもいて、少し安心しました。
最後になりましたが、
このイベントの目的は
「中南部の自然は、やんばるの自然とはまた違う特徴があって貴重だということを理解する」
「身近な自然に異変が起きた時に気づく目を養い、モニタリングすることの重要さを知る」というものでした。
ご参加された皆さんが身近な中南部の自然について考えたり、活動するきっかけになってくれれば良いなあと思います。
みんみんでも一緒に活動してくれる仲間を募集中です
【 ご紹介 田中聡先生が著者・共著の報文 】
「なわばりを守る雄 キノボリトカゲ」朝日百科 動物たちの地球102 両生類・爬虫類6 pp.178-180 朝日新聞社(1993)
「湿潤な亜熱帯の森でひっそりと生きる クロイワトカゲモドキ」 森林技術 No.766 2006.1
「レッドデータおきなわ 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第3版(動物編) 」
p193-194 キノボリトカゲ、p191-193クロイワトカゲモドキ
(URL : https://www.okinawa-ikimono.com/reddata/pdf/doubutsu2017.pdf)
Posted by 森の家みんみん at 16:19│Comments(0)
│イベントの報告
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。