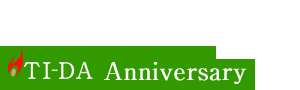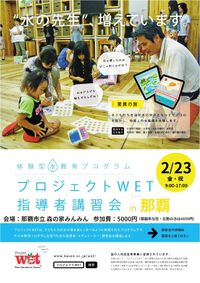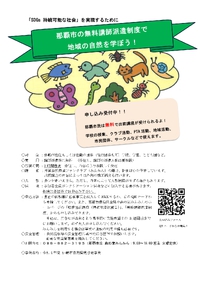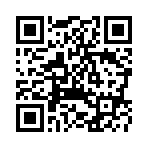2016年01月06日
雨の夜のカタツムリ
昨日の夜は、早いうちは雨が降っていましたが、夜中になって止んだので久しぶりに夜の末吉公園を散策しました。
カタツムリを幾つか写真に撮ったので紹介します。
■アフリカマイマイ
最初に見つけたのはアフリカマイマイです。 アフリカ原産の外来生物ですが、子どもでも名前を知っている沖縄で一番有名なカタツムリです。今年の夏は大きなサイズの個体が多く見られました。今日もたくさん見られると思ったのですが、意外にあまり見かけませんでした。冬は寒いからどこかに隠れているのでしょうか。 小さな個体は、クワズイモの葉の裏に付いているのをときどき見かけました。

■ウスカワマイマイ
次に目にしたのは、薄くて丸こい殻をしたウスカワマイマイです。人家や畑の周辺で普通に見られるカタツムリです。末吉公園では、林縁部で多く見られます。遊歩道の手すりや植物の茎や葉によくついています。

■パンダナマイマイ
パンダナマイマイも人家周辺で普通に見られるカタツムリです。 殻口より上の巻いている部分(螺塔)があまり膨らまないのが特徴です。
遊歩道の手すりやクワズイモの葉上よく見られました。

螺塔が膨らんでないので正面から見ると殻がとても傾いているように見えます。

クワズイモの葉上には、とても小さな個体がたくさんいました。

■シュリマイマイ
シュリマイマイは比較的大きなカタツムリです。 この日、最初は目にしなかったのですが、森の奥に入るといました。 地面にいることが多いと思うのですが、この日は直前まで雨が降っていたからなのか、手すりの上に登っているものもいました。

呼吸孔が広がっています。 カタツムリの仲間(有肺類)は、ここから空気を取り込んで呼吸しています。

■オキナワヤマタカマイマイ
樹上性のカタツムリです。ハマイヌビワ等の樹上でよく見られます。螺塔がソフトクリームのようにうず高く盛り上がっているので、ヤマタカマイマイと呼ばれています。末吉公園では、殻の白い個体がよく見られるのですが、この日はどれも色が付いている個体でした。

うず高い殻に入っているからなのか、オキナワヤマタカマイマイはとてもスマートというか細長い体をしています。

■アオミオカタニシ
緑色のカタツムリですが、普通のカタツムリ(有肺類)ではなく、タニシの仲間です。目の位置は、普通のカタツムリと違って、触角の付け根です。樹上性で、植物の幹や葉の上、手すりの上でなどにいます。 この日、大きな個体は少なかったものの、小さな個体が比較的見られました。

かなり小さな個体が、手すりや葉上で見られました。

■オキナワヤマキサゴ
とても小さくて殻の厚いカタツムリです。 オキナワヤマキサゴも普通のカタツムリ(有肺類)ではなく、また別の系統の陸産貝です。 末吉公園では、森の中の手すりやクワズイモの葉上で普通に見られます。

■食べられているカタツムリ
オキナワマドボタルが頭を殻に突っ込んで捕食していました。

ニューギニアヤリガタウズムシが巻き付いてお腹にある口で捕食していました。

散策を終えて
画像を並べるといろいろなカタツムリに出会ったように見えるが、雨上がりという条件にしては、ずいぶん少なかったというのが正直な印象である。何種類かのカタツムリについては、ここ数年で確実に数を減らしているのだと思う。今回のコースだと、シュリケマイマイを見ることはもうずいぶん前からない。学生の頃、オキナワヤマタニシが末吉公園で最も目につくカタツムリだったのに、今回はオキナワヤマタニシを写真に撮ることがなかった。カタツムリを目的に散策をしたわけではないが、目立たないくらいに減ってしまっているようだ。
カタツムリ相の変化の原因はわからないが、もう少し注意して見てみたいと思う。
カタツムリを幾つか写真に撮ったので紹介します。
■アフリカマイマイ
最初に見つけたのはアフリカマイマイです。 アフリカ原産の外来生物ですが、子どもでも名前を知っている沖縄で一番有名なカタツムリです。今年の夏は大きなサイズの個体が多く見られました。今日もたくさん見られると思ったのですが、意外にあまり見かけませんでした。冬は寒いからどこかに隠れているのでしょうか。 小さな個体は、クワズイモの葉の裏に付いているのをときどき見かけました。

■ウスカワマイマイ
次に目にしたのは、薄くて丸こい殻をしたウスカワマイマイです。人家や畑の周辺で普通に見られるカタツムリです。末吉公園では、林縁部で多く見られます。遊歩道の手すりや植物の茎や葉によくついています。

■パンダナマイマイ
パンダナマイマイも人家周辺で普通に見られるカタツムリです。 殻口より上の巻いている部分(螺塔)があまり膨らまないのが特徴です。
遊歩道の手すりやクワズイモの葉上よく見られました。

螺塔が膨らんでないので正面から見ると殻がとても傾いているように見えます。

クワズイモの葉上には、とても小さな個体がたくさんいました。

■シュリマイマイ
シュリマイマイは比較的大きなカタツムリです。 この日、最初は目にしなかったのですが、森の奥に入るといました。 地面にいることが多いと思うのですが、この日は直前まで雨が降っていたからなのか、手すりの上に登っているものもいました。

呼吸孔が広がっています。 カタツムリの仲間(有肺類)は、ここから空気を取り込んで呼吸しています。

■オキナワヤマタカマイマイ
樹上性のカタツムリです。ハマイヌビワ等の樹上でよく見られます。螺塔がソフトクリームのようにうず高く盛り上がっているので、ヤマタカマイマイと呼ばれています。末吉公園では、殻の白い個体がよく見られるのですが、この日はどれも色が付いている個体でした。

うず高い殻に入っているからなのか、オキナワヤマタカマイマイはとてもスマートというか細長い体をしています。

■アオミオカタニシ
緑色のカタツムリですが、普通のカタツムリ(有肺類)ではなく、タニシの仲間です。目の位置は、普通のカタツムリと違って、触角の付け根です。樹上性で、植物の幹や葉の上、手すりの上でなどにいます。 この日、大きな個体は少なかったものの、小さな個体が比較的見られました。

かなり小さな個体が、手すりや葉上で見られました。

■オキナワヤマキサゴ
とても小さくて殻の厚いカタツムリです。 オキナワヤマキサゴも普通のカタツムリ(有肺類)ではなく、また別の系統の陸産貝です。 末吉公園では、森の中の手すりやクワズイモの葉上で普通に見られます。

■食べられているカタツムリ
オキナワマドボタルが頭を殻に突っ込んで捕食していました。

ニューギニアヤリガタウズムシが巻き付いてお腹にある口で捕食していました。

散策を終えて
画像を並べるといろいろなカタツムリに出会ったように見えるが、雨上がりという条件にしては、ずいぶん少なかったというのが正直な印象である。何種類かのカタツムリについては、ここ数年で確実に数を減らしているのだと思う。今回のコースだと、シュリケマイマイを見ることはもうずいぶん前からない。学生の頃、オキナワヤマタニシが末吉公園で最も目につくカタツムリだったのに、今回はオキナワヤマタニシを写真に撮ることがなかった。カタツムリを目的に散策をしたわけではないが、目立たないくらいに減ってしまっているようだ。
カタツムリ相の変化の原因はわからないが、もう少し注意して見てみたいと思う。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。