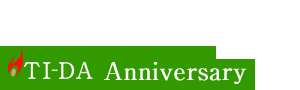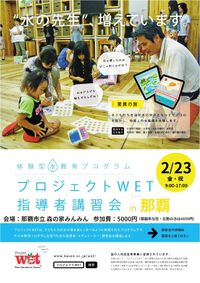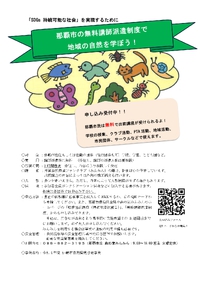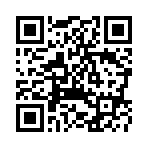2016年01月13日
ど根性オオイタビ
オオイタビは、クワ科イチジク属のツル性の木本植物で、沖縄では民家の石垣や壁、岩や樹木の幹の表面をよく覆っているのを見ることができます。 表面を覆っているときは葉っぱがとても小さいことが多いのですが、てっぺんをとったりすると枝を立てて葉っぱが大きくなり、実をつけ始めます。
末吉公園の東側の入口にある黄色いカバーの電柱の支持ケーブルにオイタビが巻き付いています。黄色いカバーの上あたりから枝を立たせて大きな葉をつけ、よく実をつけます。

今日も、実をたくさんつけています。

このオオイタビを見ながら、オオイタビってすごいと思いました。
というのも、数カ月前、誰か(公園管理者?)が、周辺の草と一緒に幹を切断しているからです。

おそらく幹を切断した人は、これでこのオオイタビが枯れると思ったのでしょう。 切られた直後は、流石にすこし勢いがなくなったかと思いましたが、いつの間にか元のように葉を茂らせて、またたくさんの実をつけています。
オオイタビは、気根でひっついています。ですから、岩や木の幹にくっついている場合は、それなりに気根から必要な水などを吸収できるだろうと予想されますが、ケーブルワイヤーでも大丈夫なんですね。

切られた幹の下(支持ケーブルの下)は岩盤で、表面を小さな葉っぱをつけたオオイタビが覆っています。随分形が違うけど、おそらく上の葉の大きなものと同一個体です。「条件さえ良ければ、いつでも枝を立てて大きな葉と実をつけてやるぞ!」と言っているようです。
末吉公園の東側の入口にある黄色いカバーの電柱の支持ケーブルにオイタビが巻き付いています。黄色いカバーの上あたりから枝を立たせて大きな葉をつけ、よく実をつけます。

今日も、実をたくさんつけています。

このオオイタビを見ながら、オオイタビってすごいと思いました。
というのも、数カ月前、誰か(公園管理者?)が、周辺の草と一緒に幹を切断しているからです。

おそらく幹を切断した人は、これでこのオオイタビが枯れると思ったのでしょう。 切られた直後は、流石にすこし勢いがなくなったかと思いましたが、いつの間にか元のように葉を茂らせて、またたくさんの実をつけています。
オオイタビは、気根でひっついています。ですから、岩や木の幹にくっついている場合は、それなりに気根から必要な水などを吸収できるだろうと予想されますが、ケーブルワイヤーでも大丈夫なんですね。

切られた幹の下(支持ケーブルの下)は岩盤で、表面を小さな葉っぱをつけたオオイタビが覆っています。随分形が違うけど、おそらく上の葉の大きなものと同一個体です。「条件さえ良ければ、いつでも枝を立てて大きな葉と実をつけてやるぞ!」と言っているようです。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。