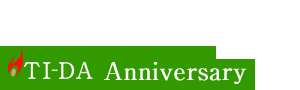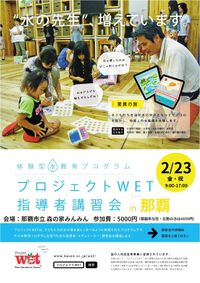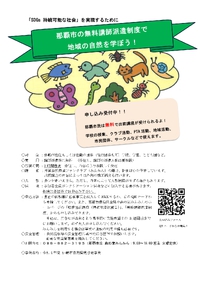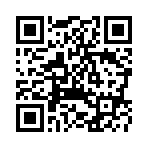2016年07月30日
南風原町神里ふれあい広場で星空観察会
昨日は、はえばるエコセンターのイベントで星空観察会があり、星あっちゃーの会の宇久さんと下地さんと一緒にお手伝いさせていただきました。
星空観察会の会場は、神里ふれあい広場ですが、星を見る前に構造改善センターのホールで宇宙の広さを体感するワークショップを行いました(そこが自分の担当です)。
まずは、身近な月について、大きさと距離について考えるワークショップです。

「この直径10㎝の玉が地球だとすると、月はどの皿にのっている玉の大きさだと思いますか。」 「これだと思う皿のところに並んでください。」
月の直径は地球のおよそ四分の一です。 10㎝の球が地球だとすると、大きなビー玉がのっている皿が正解です。 正解者は4人ですね。

「月は地球の周りをまわっています。 直径10㎝の球が地球で、大きなビー玉が月とすると、どれくらい離れたところをまわっているでしょうか。これくらいと思うところに立ってみてください。」
地球から月までの距離は38万㎞、地球の直径のおよそ30倍の距離です。 ということは、10㎝×30なので、3メートルの場所が正解です。
離れすぎている子どもたちが多いですね。

「3m離れたところから、ビー玉を見てみましょう。」
3m離れたところからビー玉を見ると、、見かけの大きさが月と同じ大きさになるはずです。
「同じ大きさに見える!」 「、見えない!」
子どもたちの意見はいろいろでした。

「このフラフープが太陽の大きさだとすると、地球はどの皿にのっている玉の大きさでしょう。」
地球の直径は、太陽の直径のおよそ100分の一です。 一番小さなビーズの球の皿に並んだ人が正解でした。
大きな球を選んだ子どもが多かったけど、やっぱり自分たちが住んでいる場所は大きく感じますよね。
ちょっと難しいけど、太陽と月の見かけ上の大きさが大体同じだということを利用して、直径5㎜の地球(ビーズ玉)から太陽がどれくらい離れているか考えました。 月の直径は太陽の直径のおよそ400分の一です。ということは、同じ大きさに見えるためには400倍離れていることになります。5㎜の地球から月までの距離は、5×30=15㎝です。ということは、15×400=6000cm、つまり、60m離れたところに太陽があることになります。

実際に、巻き尺で測って60m先まで行こうとしましたが、40メートル先までしか行けませんでした。

ワークショップの締めとして、星の大きさ比べや宇宙の果てまでの旅のCG動画を見ました。
想像を絶する、宇宙空間のスケールの大きさに圧倒されたところで、ふれあい広場に移動して星空観察を始めました。


みんな機材のセッティングを待てないくらい、星を見たくなっています。 セッティングが終わったら外灯も消してもらいました。
この日は、直前まで雨で、曇っていたので、どうなることかと思いましたが、だんだん天気が回復して、夏の大三角、さそり座、木星、火星、土星などを楽しく見ることができました。特に、土星は人気で、2台の望遠鏡には何回も何回も見たがる子どもたちの列ができていました。
親子で星空観察会をやると、途中で子どもたちが飽きてきて親だけが見ているなんてこともあるのですが、最後までというより、希望により時間を延長してまで、みんなが楽しく星を見ることができたのはとても良かったです。
宇久さん、下地さん、みんみんでやるときもよろしくお願いします。
(ふじい)
星空観察会の会場は、神里ふれあい広場ですが、星を見る前に構造改善センターのホールで宇宙の広さを体感するワークショップを行いました(そこが自分の担当です)。
まずは、身近な月について、大きさと距離について考えるワークショップです。
「この直径10㎝の玉が地球だとすると、月はどの皿にのっている玉の大きさだと思いますか。」 「これだと思う皿のところに並んでください。」
月の直径は地球のおよそ四分の一です。 10㎝の球が地球だとすると、大きなビー玉がのっている皿が正解です。 正解者は4人ですね。
「月は地球の周りをまわっています。 直径10㎝の球が地球で、大きなビー玉が月とすると、どれくらい離れたところをまわっているでしょうか。これくらいと思うところに立ってみてください。」
地球から月までの距離は38万㎞、地球の直径のおよそ30倍の距離です。 ということは、10㎝×30なので、3メートルの場所が正解です。
離れすぎている子どもたちが多いですね。
「3m離れたところから、ビー玉を見てみましょう。」
3m離れたところからビー玉を見ると、、見かけの大きさが月と同じ大きさになるはずです。
「同じ大きさに見える!」 「、見えない!」
子どもたちの意見はいろいろでした。
「このフラフープが太陽の大きさだとすると、地球はどの皿にのっている玉の大きさでしょう。」
地球の直径は、太陽の直径のおよそ100分の一です。 一番小さなビーズの球の皿に並んだ人が正解でした。
大きな球を選んだ子どもが多かったけど、やっぱり自分たちが住んでいる場所は大きく感じますよね。
ちょっと難しいけど、太陽と月の見かけ上の大きさが大体同じだということを利用して、直径5㎜の地球(ビーズ玉)から太陽がどれくらい離れているか考えました。 月の直径は太陽の直径のおよそ400分の一です。ということは、同じ大きさに見えるためには400倍離れていることになります。5㎜の地球から月までの距離は、5×30=15㎝です。ということは、15×400=6000cm、つまり、60m離れたところに太陽があることになります。
実際に、巻き尺で測って60m先まで行こうとしましたが、40メートル先までしか行けませんでした。
ワークショップの締めとして、星の大きさ比べや宇宙の果てまでの旅のCG動画を見ました。
想像を絶する、宇宙空間のスケールの大きさに圧倒されたところで、ふれあい広場に移動して星空観察を始めました。
みんな機材のセッティングを待てないくらい、星を見たくなっています。 セッティングが終わったら外灯も消してもらいました。
この日は、直前まで雨で、曇っていたので、どうなることかと思いましたが、だんだん天気が回復して、夏の大三角、さそり座、木星、火星、土星などを楽しく見ることができました。特に、土星は人気で、2台の望遠鏡には何回も何回も見たがる子どもたちの列ができていました。
親子で星空観察会をやると、途中で子どもたちが飽きてきて親だけが見ているなんてこともあるのですが、最後までというより、希望により時間を延長してまで、みんなが楽しく星を見ることができたのはとても良かったです。
宇久さん、下地さん、みんみんでやるときもよろしくお願いします。
(ふじい)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。